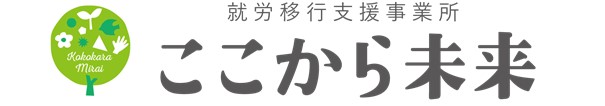Texture 13 三渓園及び原三渓について

皆様常日頃誠にお疲れ様です。先週金曜日に記載させていただいた三渓園の歴史が非常に興味深く思いましたので、縮尺・配置の異なる三渓園周辺図を貼り、引き続き三渓園の話題を広げて参ります。
三渓園は、埼玉県児玉郡神川町の豊かな農家(醸造業・質屋兼業)に生まれた実業家・政治家原善三郎(1827年5月23日(江戸時代後半)~1899年2月6日)が、神奈川県横浜市で生糸売込問屋「亀屋」を開業したことを機に諸事業(横浜為替会社頭取就任、横浜生糸改会社社長就任、横浜銀行の前身第二国立銀行頭取就任、JR横浜線の前身横浜鉄道設立)を展開して財産を築き、1868年(明治元年)頃に横浜市中区本牧三之谷の広大な土地を購入したことから始まります。その後、原善三郎は、1889年に横浜市会初代議長に就任(同年栄典銀製黄綬褒章)、1892年に衆議院議員に当選、1897年に貴族院多額納税者議員に就任、没年に従五位の位階を賜りました(横浜商工会議所の前身横浜商法会議所初代会頭、横浜蚕糸売込業組合初代頭取にも就任)。
原三渓(本名富太郎。三渓は茶人としての号。岐阜県岐阜市柳津町渡庄屋青木家の長男。早稲田大学を卒業後に跡見女学校教師に就職)は、原善三郎の孫娘原屋寿(同女学校教師時代の生徒)と結婚して原家の婿養子となり、家業を発展させます。1906年5月に善三郎の購入した本牧三之谷の土地の外苑を三渓園として開園(それ以前から善三郎共々、山荘や本宅を建てて古建築を蒐集、造園を本格的に進めていました。山荘松風閣は善三郎、本宅鶴翔閣は富太郎が建て、古建築「旧天瑞寺寿塔覆堂」入手も行った頃から三渓の号を名乗るようになりました)して無料で公開、更に新たな屋敷の建築や由緒ある古建築や美術品の蒐集を進め、支援・交流していた画家に作品を制作させました。三渓は、文化保護・振興、横浜市都市基盤整備、弱者救済のための社会福祉も実施、関東大震災後には横浜市復興会長に就任して私財を投じて復興を進め、横浜の恩人と称されます(1925年の神奈川県直接国税総納額は県内1位でした)。三渓園や原家各邸宅は第2次世界大戦の空襲で大きな被害を受けますが、戦後に復旧し、公開・運営のために財団法人三渓園保勝会が設立されました。同会は原家から土地の大部分を譲り受け、復旧完了後に内苑も公開、宗徧流林洞会から茶室「林洞庵」が寄贈され、臨春閣(紀州徳川家の別荘「巌出御殿」と考えられる古建築で、1917年(大正6年)に移築完了)に新たに障壁画(中島清之・千波筆)を制作、聴秋閣奥の渓流沿い遊歩道を復元し、以後、季節公開、“燈明寺本堂”の移築を開始(1987年工事完了)、1989年には三渓記念館を開館して三渓に関する資料や収集品等を展示し、2000年には「鶴翔閣」を整備・復元し、2007年に国の名勝に指定され、現在に至ります。茶室「林洞庵」寄贈時には、その隣接地が本牧市民公園となり、南門を設けました。父と行った際に中華風の小山やあずまやがあった公園のような場所にも入りました(三渓園入園の前か後かは忘れました)が、おそらくはこの本牧市民公園と思われます。
今回は以上です。お読みいただき誠に有難うございます。つつがなき日々でありますように。
お問い合わせ
障害をお持ちの方で支援を受けて就職につなげたい方、自分の強みを生かしたい方にお勧めしております。
もっとくわしく情報が欲しい人はこちらからお問い合わせ下さい。